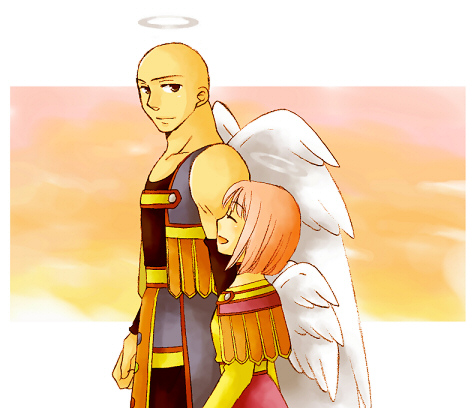『夕涼み』 ※挿絵なしはこちら
神の在す天空には、神が創りし荘厳な白亜の島が漂うという。
そこには神の御使が住まい、神の手足となりて人を守り救い給うという。
「……というわけだ。では、再び参るぞ」
「はい、お師匠さま」
そんな伝説上の存在である天使も、神が創りし存在にて所謂人間の上位にあたる存在。すべからく天使は先に創られた人間に似る。
つまりは、天使も人間も、本質は同じである。
「そうではない。……こう、持つのだ。しっかりと脇を引き締めて……関節を痛めてしまわないように」
「はい、お師匠さま」
ここに、弟子に異様に甘い師と、師に異様に懐いている弟子がいる。
「……疲れたか?」
「いいえ、大丈夫です」
その甘い頬の輪郭、零れるような祝福の笑顔。それも剣の修行にいざ参らんとするとき、鋭く真剣な眼差しとなる。
「……っ!!」
「私を見なさい!対峙する相手から目を離してはいけない!」
師の太刀筋は迷いが無い。脇を引き締め剣を両手で握る。剣戟を数度繰り返した後、振り上げた師の剣先が目前に迫った瞬間を見定め、切り上げる――
大きな痺れが腕を伝う筈が、自分の握る剣と懐の間に突かれた師の剣先。身動きが取れない。
「……参りました」
「今の間合いは良かった。但し踏み込みが甘い。……こう、だ」
先程の弟子の立場となって師が動く。
「相手の剣がこう、振り下ろされる。ここから切り上げるには、もっと間合いを詰める。……こう、だ。もっと近づけば相手は腕と視界の自由を失う」
互いの息づかいさえ届く、数センチ先の汗と温度。
「それでは、今日はこれまで」
「はい、イザヤールさま、ありがとうございました!」
互いに一礼する。顔を上げたときにはまたあの柔らかい微笑みが戻る、夏のとある夕方。
「……これから少し時間はあるか?」
「はい、今日の課題はもう終わりました」
「そうか。では少し私につき合ってもらおう」
行政街区外れの神殿の一つが、守護天使用の武術道場として割り当てられている。
付属の水浴び場にて手早く汗を流し、神殿前の石段を二人で降りれば、心地よい風が肌を撫でる。
遠く傾く太陽は、雲間から二人を橙色に照らした。
「随分強くなったな」
「……ありがとうございます」
「他の天使と剣を交えてみたら、楽しいことになりそうだ」
微かに笑い、弟子を見る。弟子の才能を引き出すのは、師としての喜びだ。そして自分の弟子の強さは、師である自分がよくわかっている。
「お師匠さまのように、強くなりたいです」
そして、この弟子は素直で愛くるしい。
「ああ、強くなれ」
夕焼けに染まる肌は、汗も飛んで滑らかに輝くようだ。この弟子を、いつまでも見守りたいと思う。
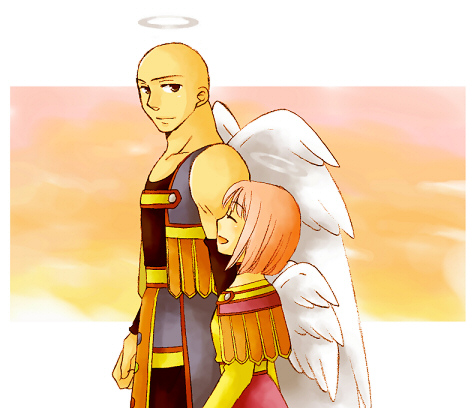
***************
「ラフェットのところで本を借りねばならないのだが……暇を見つけてお前を連れてこいとうるさいのだ」
「? ラフェット様がですか?」
「何か急ぎでない用事でもあるのだろう」
ラフェットの私宅は居住区の中の簡素な木造家屋の中にある。『敷地の手入れをする暇が勿体無い』というラフェットは、長年その一角に住み続けていた。
今日は、休日で弟子と共に私宅でのんびりと過ごしているという。呼び鈴を鳴らして玄関に出てきた彼女は、いつもの文官の執務服ではなく、ラフなパンツルックにエプロンをしていた。
「いらっしゃい、どうぞ」
「いつも悪いな」
「気にしないで。……あら!今日は嬉しいことばかりね、いらっしゃい」
「お邪魔いたします」
いつ来ても無駄なものが殆ど無い室内。ガラス窓から差し込む夕日が、青竹を細く削って編んだ簾に遮られ、落ち着いた風情を醸し出す。
黒光りする壁と床の木の板は涼しげで、柱に掛かった漆器の一輪挿しには赤紫色の花をつけた野草が挿してあった。
「……素敵」
思わず溜息をつく。見たことの無い内装は、何故か懐かしい。
文官であるラフェットの趣味は、人間界各地の風俗文化に関する読書。そしてその中でも取り分け、カルバド大草原の東南にある名もない島国の情緒を愛した。
「ありがとう。これはね、『竹』という植物を加工して作られているの」
「すごい、です。初めて見ました」
目をキラキラと輝かせている弟子。初めて訪問する上級天使の私宅をつぶさに観察する訳にもいかず、好奇心を持て余し緊張している。
ラフェットが本を数冊、奥の書庫から持ってきた。
「はい、これね。あと……ちょっと待っててくれる? ……ちょっとー、来てくれる――?」
「はーい、お師匠さま只今ー」
隣室から出てきたのは彼女の弟子。肩までの黒髪を赤い飾り紐で二つに結って、涼し気な白地に美しい朝顔の花を咲かせた柄の衣を纏っている。
「ほう。これは……?」
「今日やっとできあがったの。『浴衣』っていうのよ」
「器用なものだ」
「涼し気できれいでしょう。あなたのお弟子さんにもあげようかと思って。――ねえ、どう?着てみない?」
見たことの無い清楚な衣に目を奪われていた弟子は、零れんばかりに両目を見開き、大きく瞬きをする。
「……は、はい!」
「よかったあ。もう、ね。女の子を弟子に取ったら、大抵着せ替え人形にするのが楽しみっていうのに。あなたのお師匠様まるっきりそういうこと無頓着なんだもの」
それじゃあ可哀想よねえ、と嬉しそうに奥から布の包みを持ってくる。
「あなたにあげる。着せてあげるからこっちに来て。イザヤール、彼女借りるわ」
「あ……ああ」
弟子とラフェットと彼女の弟子。三人がラフェットの寝室に入ってしまい、イザヤールは手持ち無沙汰に出された茶をすすった。
(あんな嬉しそうな顔――)
公私混同は良くない、とイザヤールは思う。しかしやはり何か欠けているところがあるのかもしれない、と少しさみしい気持ちが芽生える。
奥の部屋からはきゃっきゃっとはしゃぐ声が聞こえて、弟子が一体どんなことになっているのか、想像に難くない。
軒に吊るされた鉄製の装飾品が、ちりん、と涼風を運んだ。
→ next